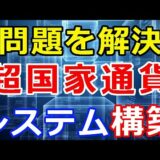2025年はビットコインをはじめ、リップルのようなアルトコインまでもが史上最高値を更新。各暗号資産(仮想通貨)の現物ETFが数ヶ月以内にSECから承認の可能性も囁かれており、多くの投資家が暗号資産の今後の行方に期待を膨らませています。
そして、投資家たちはこのバブルに波乗りしようと、仮想通貨の上場予定一覧にあるような新たな銘柄にも着目。専門家チームが分析した一覧を元に、有望銘柄を着実に見極めています。
一方で、このように暗号資産への投資が一般化する中で、どの取引所を利用するかは資産を安全に保護できるか否かの問題に直結します。2020年代に入ってからも、FTXの破綻やハッキングによる資産流出など、サービスが停止に追い込まれるようなケースも発生しています。したがって、このようなリスクを避けるためには、事前に取引所の安全性を多角的に評価する必要があります。
では、どのようにして安全な取引所を見分ければ良いのでしょうか。本記事では、投資家の視点から暗号資産取引所の信頼性を判別する具体的なポイントを解説します。
セキュリティ対策の水準
取引所がどのようなセキュリティ対策を講じているかは、最も基本的でありながら重要な確認ポイントです。そして、複数あるセキュリティ対策の中でもまず注目すべきは、顧客資産の保管方法です。
優良な取引所の場合は、資産の大部分をインターネットから切り離された「コールドウォレット」で管理し、オンライン上のホットウォレットには最小限の資産しか置かないようにしています。これは万が一、サイバー攻撃を受けた際の被害を最小限に抑えるためです。
さらに、マルチシグと呼ばれる複数署名の技術を導入している取引所であれば、1つの鍵が流出したとしても、即座に資産が移動されるリスクを軽減させることができます。
加えて、「2段階認証」を必須としているか、あらかじめ登録したアドレス以外への送金をブロックする「ホワイトリスト機能」を採用しているかも要チェックです。また、技術的セキュリティだけでなく、「ISO 27001」などの国際的なセキュリティ認証を受けているかどうかも、セキュリティに対する姿勢を測る指標になるでしょう。
規制とライセンスの有無
次に確認すべきポイントは、取引所がどこの国でどのようなライセンスを取得しているかという点です。
たとえば、日本国内で暗号資産を取り扱う取引所には、金融庁への登録が義務付けられています。実際に、国内取引所として著名なbitFlyerやbitbankなどの取引所はこの登録を受けており、規制の枠内で運営されています。金融庁も、取引を行う際には登録済みの事業者であるかどうかの確認を行うように、注意喚起を行っています。
なお、日本国外の取引所を利用する際には、ニューヨーク州金融サービス局やシンガポール金融管理局など、信頼度の高い監督機関からライセンスを取得しているかを確認する必要があります。
また、ライセンスの取得状況だけでなく、KYCやマネーロンダリング対策を徹底しているかも、安全な取引所であるかの判断材料となります。これらを実施していない取引所は、匿名性の高さを逆手にとって不正利用されるリスクがあり、結果的にユーザー全体が損を被る恐れがあるのです。
さらに、規制のある取引所では監査の実施や運営報告の提出も義務づけられているため、経営の透明性にもつながると言えます。長期的に取引を続ける予定の投資家ほど、ライセンス取得の有無はしっかり確認しておくようにしましょう。
保険や補償の体制の有無
先述のセキュリティ対策は一般的に確認すべき事項ですが、必ずしもハッキング被害を免れられるとは限りません。日々新たな技術が誕生し、セキュリティを掻い潜るような技術も生まれているからです。
そのため、有事の際にユーザー資産を補償する体制が整っているかどうかも重要です。たとえば、Binanceでは「SAFU」という独自の保険基金を設けており、2019年に発生したハッキング事件ではこれを活用して全額補償を行いました。また、CoinbaseやMEXCなど一部の取引所では、第三者の保険会社と提携し、盗難や従業員による不正行為に備えた保険を用意しています。
また、日本円や米ドルなど法定通貨を取引所に預ける場合には、そのお金が信託口座に分けて保管されているか、あるいは米国の預金保険制度など公的な保護の対象になっているかを確認することも大切です。これらの仕組みがあれば、万が一取引所が破綻しても、預けたお金が返ってくる可能性が高くなります。
こうした保証制度は、最悪の事態が起きた際に利用者の損失を最小限に抑える重要なセーフティネットとなるため、安全性を評価するうえで、必ず確認しておいてください。
情報公開の透明性と運営の信頼性
安全とされる取引所は、運営情報や財務状況を積極的に公開しています。会社の所在地や経営陣の実名、さらに資産証明や外部監査報告書の有無などが、運営に対する信頼性を高めます。特に、第三者機関による監査を受けた証明書を定期的に公開している取引所は、顧客資産の健全な管理に自信を持っていると考えてよいでしょう。
また、経営陣の顔が表に出ており、どのような経歴を持っているかが明らかになっていることも大きなポイントです。顔の見える運営は、責任の所在がはっきりしており、信頼性を裏付けるといえます。加えて、プライバシーポリシーが多言語で丁寧に説明されているかどうかも、ユーザー保護への姿勢を測る判断材料になるでしょう。
ユーザーの声と過去の実績
最後に、実際の取引所ユーザーからの評価も重要な情報源です。SNSやレビューサイト、暗号資産関連のフォーラムなどを活用することで、ユーザーの生の声をチェックし、過去に出金遅延やカスタマーサポートの不備がなかったかを調べておきましょう。また、ハッキングなどの過去事例がある場合は、その後の対応が迅速で誠実だったかどうかが信頼を左右します。
また、取引所によっては、アプリの使いやすさやサポート対応の質など、表に出にくい部分での評価が分かれることもあります。情報発信の頻度やユーザー教育コンテンツの充実度なども総合的に見て、安全性と信頼性を評価するのが賢明です。